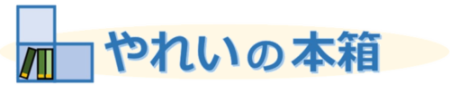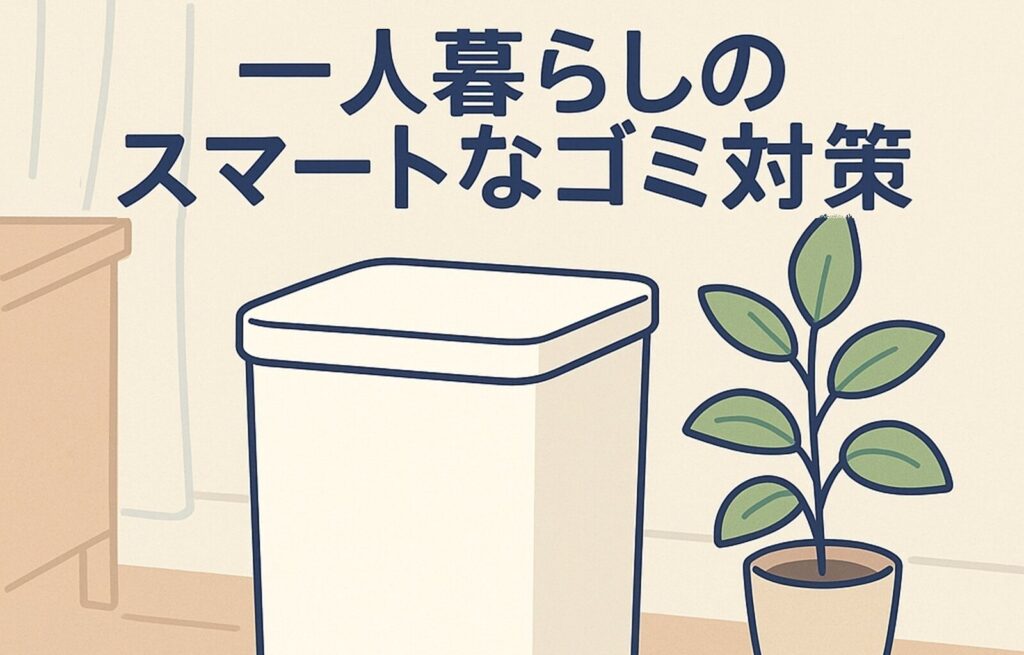一人暮らしの大きな悩みの1つが、ゴミの管理です。
限られた狭いスペースで生活する一人暮らしでは、ゴミの扱い方は特に気をつける必要があります。
収集日まで適切にゴミを管理できないと、ゴミ箱からの臭いが気になって在宅勤務に集中できなかったり、部屋にコバエが入ってくる事態に!
この記事では、一人暮らしが特に悩みやすい「ゴミの臭いに困らない管理方法」を具体的な方法とともに徹底解説します。
結論として、ゴミはこまめに出し、密閉袋も活用して臭いを防ぎましょう!
ゴミの臭いやコバエが発生する原因は?夏場は特に要注意!
環境省の「一般廃棄物処理事業実態調査(令和3年度)」によると、1人1日当たりのごみ排出量は、890グラムほど1。
毎日すべてのゴミを自宅で捨てているケースは少ないと思いますが、それでも生活している以上、ゴミは日々たまります。
そして、家のゴミは外に捨てるまで、臭いの問題がつきまとう!
ゴミの臭いは温度や湿度が高いほど発生しやすく、対策しないとコバエも寄ってきます…。
特に夏場や梅雨時は、ゴミに潜む細菌の活動が活発になり腐敗が進みやすく、臭い対策は必須!
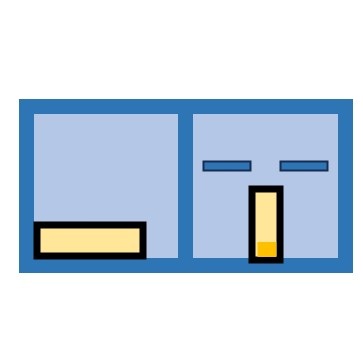
乾燥している冬は、臭い対策は不要ってこと?
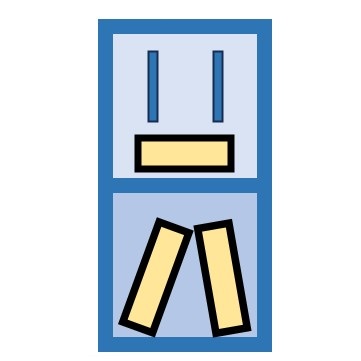
季節に関係なく対策しよう!
冬場も、部屋を閉め切っていたり、暖房器具で室内が暖かくなったりするから、過信は禁物だよ。
気温や湿度だけでなく、ゴミに付着した水分や油分も、雑菌やカビが増殖しやすくなる原因に。
特に生ゴミやプラゴミ(食品トレー、パック、調味料の容器など)は、臭いの温床になりやすいです。
生ゴミやプラゴミの臭いを抑えるにはどうすればよいか、具体的に見ていきましょう。
生ゴミの捨て方
生ゴミは、ゴミの中でも特に要注意!
水分が多い野菜・果物の皮や切れ端、魚や肉の残りなどは腐敗スピードが早く、捨て方を工夫しなければすぐに臭い始めます。
捨て方のポイントを5つ紹介していきます。
ポイント① キッチンシンクに三角コーナーを設置しない
私のおすすめは、キッチンシンクに三角コーナーは置かずに、使い捨て式の生ゴミ入れを代わりに使うこと!
三角コーナーはぬめりや臭いを防ぐためにこまめに掃除しなければならず、メンテナンスがとにかく大変です。
100均の店などには、使い捨て式のゴミ袋を取り付けられるダストホルダーや、袋そのものが自立する使い捨ての水切りゴミ袋などが販売されています。
使い捨て式のゴミ袋なら、生ゴミを袋ごとゴミ箱に捨てられ、非常に便利!三角コーナーいらずで快適です。
ただし、使い捨てのゴミ入れも、調理後は水気を切って、すぐゴミ箱に捨てるようにしましょう。出しっぱなしはNG!
ポイント② 水分を切る
ゴミを捨てる前に、生ゴミの水分を切ることも重要!
水分の多いゴミは、ゴミ箱にそのまま捨てるとゴミ袋が重みで破れたり、液漏れのリスクが高まります。
生ゴミはボタボタ垂れないくらいに水分が切れてから、ゴミ箱に捨てましょう。
ポイント③ 新聞紙などの紙に水分や湿気を吸わせる
野菜の皮を紙でくるんでから捨てたり、新聞紙をゴミ箱に敷いて、水分や湿気を紙に吸い込ませましょう。
吸水すれば、臭いの発生はぐっと抑えられます。
新聞紙が手元になくても、以下のような家にあるもので代用できます。
- 使わなくなったノートやメモ帳、コピー用紙の裏紙
- ポストに届く不要なチラシ
- 買い物でもらった紙袋
- キッチンペーパー
チラシといっても、コーティングされたツルツルの紙や写真用紙は水を吸いにくいため不向きです。
ポイント④ 重曹や消臭アイテムを使う
ゴミ箱の消臭アイテムは、さまざまなタイプが販売されています。
- 貼るタイプ:ゴミ箱のフタ裏に貼って使用。コンパクトで邪魔になりにくい。
- 吊り下げタイプ:ゴミ箱のフチに吊り下げて使用。フタ裏に貼れる2wayタイプも。
- スプレータイプ:一時的にニオイを抑制したい場合に便利。
- シートタイプ:ゴミ箱の底面に敷いて、悪臭の原因となる液だれを吸収。
- 粉タイプ:直接ふりかけるだけ。
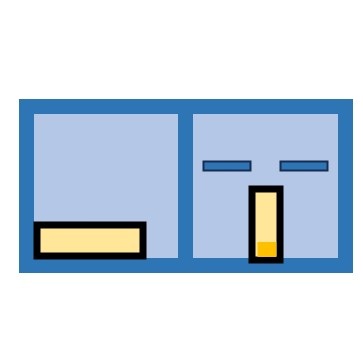
香りはどれを選べばいいんだろう?
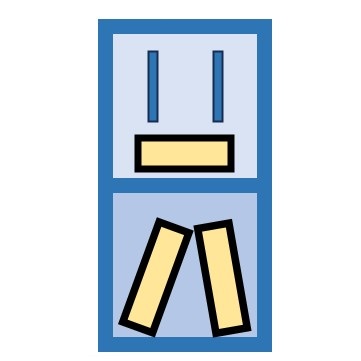
迷ったら無香タイプがおすすめ!
強い臭いには強い香りを!という力業だと、かえって臭いがキツく感じることも…。
ポイント⑤ ゴミ箱を密閉式にする
臭い対策で効果的なのは、しっかり蓋が閉まる密閉ゴミ箱。少しでも隙間があると、意外と臭いが外に漏れてしまいます。
生ゴミを捨てるゴミ箱は、スイング式よりもパッキン付きや横に開くシャッター式のものがおすすめです。
プラゴミの捨て方
意外と厄介なプラスチックのゴミ。
食品トレー、ヨーグルトや納豆の容器、調味料のボトルなども、生ゴミと同様に臭いの元になります。
ポイント① 軽くきれいにしてから捨てる
洗剤などでピカピカにする必要はありませんが、次の3点を意識すると臭いの発生を抑制できます。
- 中の液体をしっかり出す
- サッと水洗いする
- 油っぽいものは、古紙やキッチンペーパーで拭く
ポイント② 乾かしてからゴミ袋へ捨てる
濡れたまま捨てると、臭いの原因になるだけでなく、袋の底がヌルヌルに…。
プラゴミは、水切りラックなどで軽く乾かしてからゴミ袋に入れるのがベストです。
ポイント③ 週に1回はプラゴミの袋ごと交換
溜まりやすいけれどつい後回しにしがちなプラゴミですが、週1回は収集日に必ず捨てるようにしましょう。
その際、プラゴミのゴミ袋は使い回さず、新しい袋に取り替えることもポイント。
プラゴミは週に一回収集に来る自治体が多いです。収集日を忘れないようにしましょう!
お手軽な臭い対策!使用済みジップロックをゴミ入れに有効活用
私が特におすすめしたい、手軽に臭いを抑える方法はズバリ、「密閉できる袋にゴミを詰めてからゴミ箱の袋に捨てる」です。
納豆の容器などは、そのまま捨てると臭いが強く、かといって毎回容器を洗うのは大変!
そんなときはゴミを、冷凍野菜などを入れていた使用済みの冷凍保存袋(ジップロックなど)に入れてからゴミ箱の袋へ!洗う手間なく、臭いを抑えたまま、収集日を迎えられます。
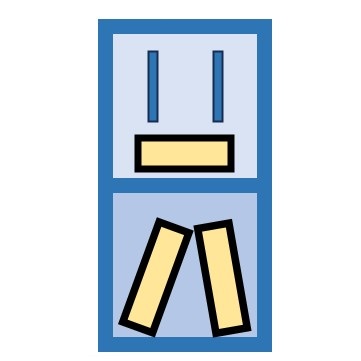
使用済みの冷凍保存袋でゴミ入れに使えそうなものは、冷蔵庫に畳んでとっておこう!
ただし、汚れが目立つ使用済みの袋は、ゴミ入れに再利用せずそのまま処分しよう。


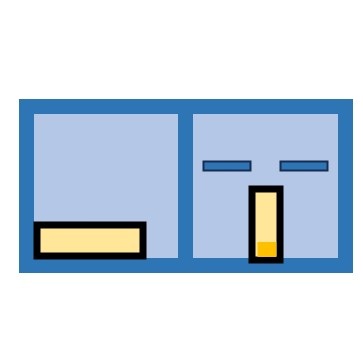
冷凍保存袋は持ってないや。代用できる物が部屋にあるかなぁ。
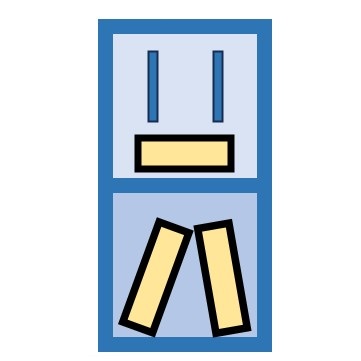
プラゴミだったら、例えば個包装のお菓子が入っていたお菓子袋も活用できるよ!
テープや輪ゴムで口を閉じるようにしよう。
ゴミをためないコツを3つ紹介!収集日に確実に捨てるために
ゴミをためないためのコツを3点紹介します。
- ゴミ収集日を毎日視界に入るところに貼る
- 収集日の朝にリマインダーを設定する
- ゴミ袋は小さいサイズを使う
ゴミ収集日を毎日視界に入るところに貼る
ゴミの収集は自治体によって頻度や曜日が異なります。
ゴミの収集日の一覧表を、冷蔵庫の正面扉など毎日視界に入るところに貼るのがおすすめ!
スマホなど、常に携帯している端末のカレンダーに収集日を登録するのも効果的です。
特に引越し直後は、引越前の収集日と間違えてしまいがち!
慣れてきても、曜日の感覚がずれて収集日を間違えてしまうこともあります。収集日はいつでもチェックできる状態にしておきましょう。
収集日の朝にリマインダーを設定する
ゴミの収集日には、 アラームが鳴るようにスマホにリマインダーを設定するとよいです。
各自治体で決められているゴミを出す時間のギリギリに設定するのではなく、15分前など余裕を持って設定するのがおすすめ。
私の場合、8時00分までにゴミを出すのが自治体のルールですが、7時20分にアラームを設定しています。出勤する時間の7時30分に合わせて、家を出る時間の10分前に設定しているからです。
変則的に在宅勤務の日もありますが、鳴らす時間はいつも固定にしたほうが、アラーム設定の手間が省け、ゴミを出すタイミングが体に染み付きます!
ゴミ袋は小さいサイズを使う
一人暮らしなら大容量よりも、こまめに捨てられる小サイズが便利!
40リットル以上の大きいサイズだと一人分のゴミで袋が満タンになるまで時間がかかり、「次の収集日でいいや!」とため込む癖がついてしまいます。
可燃ごみの収集日は、週2回に設定されている自治体が多いです。都内でもほとんどの区が、週に2回収集されています(武蔵野市ごみ収集の在り方等検討委員会(平成28年1月~平成30年9月) 最終報告書より)。
収集日が来る度にゴミを出すのが理想的のため、生ゴミを含む可燃ゴミは2、3日分を溜められる20L前後の袋がおすすめ!
プラゴミは20L~30L程度の袋がおすすめです。収集は週に1回としている自治体が多く、プラスチックの容器は可燃ゴミよりもかさばるためです。
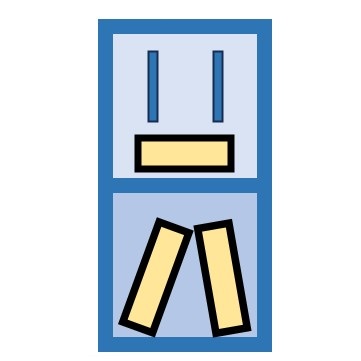
自治体によってはゴミ出し用の袋が厳密に指定されていることも。
ゴミの分別方法と合わせて、必ず各自治体のルールを確認しよう!
省スペースなごみ管理術!ゴミ箱の設置方法を工夫して快適に
一人暮らしの部屋にゴミ箱はいくつ必要?
まずは可燃ゴミとプラゴミ用に2つ設置し、自治体の分別方法やライフスタイルに合わせて、適宜ゴミ箱の数を調整しましょう。
1例として、私は1Kの賃貸物件に住んでいますが、次のような管理をしています。
| 設置場所 | ゴミ種別 | 保管方法 | メモ |
| 6畳間 | 可燃ゴミ | 高さ30cm未満のゴミ箱 | お菓子の包装紙など臭いが出るものは、キッチンのゴミ箱のほうへ。 |
| キッチンの玄関そば | 生ゴミや衛生ゴミ | 20Lのゴミ箱 | 収集日に6畳間の可燃ゴミとまとめてゴミ出し。 |
| キッチンの玄関そば | プラゴミ | 20Lのゴミ箱 | ゴミ袋自体はひとまわり大きい30L。(収集日に、冷蔵庫に入れていたプラゴミの入ったジップロックも一緒に捨てるため。) |
| キッチンの玄関そば | 段ボールや古紙 | 買い物でもらった紙袋 | 大きい段ボールは束ねて紙袋のそばに配置。 |
| キッチンの玄関そば | 缶やペットボトル | ゴミ箱なし | ほとんどゴミが出ないため、出たときだけ小さめの袋に入れ管理。 |
ゴミ箱の設置場所はどこがおすすめ?
ゴミ箱の置く場所は玄関近くがおすすめ!理由は次の3つです。
- 生活スペースから離れた場所のため、臭いが気になりにくい。
- ゴミ出しを忘れて慌てて家に戻ったとき、すぐに取り出しやすい。
- いらない郵便物を、生活スペースに持ち込まずに捨てられる。

狭い部屋でもできる!省スペース術2選
ゴミ箱を複数設置するスペースがない場合は、次の収納方法を検討してみましょう。
- 方法①:縦に分けるタイプのゴミ箱を使う
ゴミ箱を横に並べると場所を取りますが、縦に重ねられるタイプのゴミ箱なら省スペース。1段ずつゴミ袋を入れ替えられる設計のものがおすすめです。
新輝合成のトンボブランドのユニードシリーズは、様々なサイズ、段数から選べるため、あなたの自炊頻度や生活スタイルに合ったサイズを選べます。
容量が36Lの2段式の場合は、上段が20.5Lで下段が15.5Lです。
例えば、かさばるプラゴミを上段に、可燃ゴミを下段に捨て、それ以外のゴミ用にゴミ箱脇のフックに袋を吊り下げることができます。
- 方法②:袋だけ分けて1つのゴミ箱に集約する
ゴミ箱を何個も置くのが難しいときは、1つのゴミ箱の中で袋を分けて使う方法も。家の中でゴミがあまり出ない人向けの方法です。
例えば大きめのゴミ箱を1つ用意して、左半分を可燃ごみ用の袋、右半分をプラごみ用の袋というふうに仕切ってしまえば、2つのゴミ箱を設置するより省スペース!
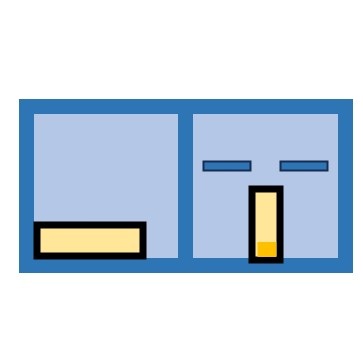
プラごみとか缶・ペットボトルのゴミ袋は、ベランダに置くのもありなのかな。
部屋が小さすぎて室内に置けなさそうで…。
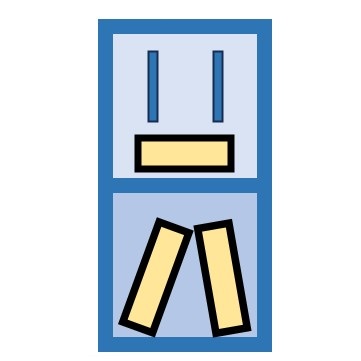
なるべくやめておこう!
ベランダに保管すると室内は快適だけど、風で飛んでしまったり、臭い対策が不十分だとご近所さんにご迷惑がかかるし、虫を呼ぶ原因にもなるよ。
まとめ:ゴミの適切な管理で快適な一人暮らしを!
本記事では、主に以下の内容についてご紹介しました。
- ゴミは収集日の度にこまめに出す。
- 水分の多いゴミは軽く水を切ったり、紙に水分を吸わせてから捨てる。
- 臭いやすいゴミは、密閉できる袋に詰めてからゴミ袋に捨てる。
- ゴミ箱はまず生ゴミ・プラゴミ用に2つ用意して、ライフスタイルに合わせ数を調整する。
一人暮らしだと、どうしてもゴミ出しが後回しになったり、捨て方がぞんざいになってしまうもの。ですが、ちょっとした工夫で部屋の快適度は格段にアップします!
ゴミを適切に管理して、スッキリ快適な部屋をキープしていきましょう!
ゴミの臭い対策のためにも、湿度が高い時期の部屋の湿気対策は欠かせません。湿気の対策方法はこちらの記事にまとめています。
- (参照日時:2025/08/05 20:30)https://www.env.go.jp/press/press_01383.html ↩︎