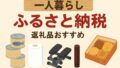「実家では家族が防災の備えをしてくれたけど、どんなものを揃えておけばいいんだろう…」
そんな風に悩んでいませんか?
一人暮らしに限った話ではありませんが、手っ取り早いのは、「必要なものが一式揃った防災リュック」を買ってしまうこと。
忙しい社会人にとって、一から全てを揃える手間や時間が省けるのはありがたい!
この記事では、私が実際に一人暮らしを始めてから購入した防災リュックの紹介と、「プラスα」の備えについてご紹介していきます。
”もしも”のときが本当に来る前に、自分で備えられる範囲のものは備えておきましょう!
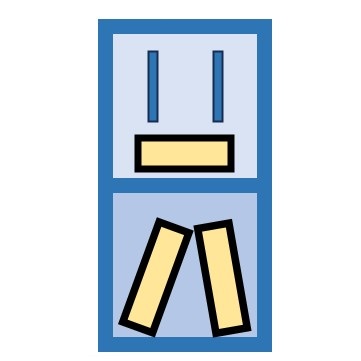
この記事は、こんな方におすすめ!
- 災害時の備えをしておきたいけれど、何をすればいいか悩んでいる方
- 必要なものが一通り揃った防災リュックを探している方
- 防災リュックは購入済みだが、「何が入ってたっけ?」状態の方
一人暮らしの防災は「セットになった防災リュック」がおすすめな理由
結論から言うと、何かと忙しい一人暮らしの社会人に便利なのが、必要なものが一通りセットになっている防災リュックです。
私の場合、防災リュックは最初、自分が持っているリュックを防災リュックとして、自分で中身を1つずつ準備したほうが安上がりだろうと考えて、一から準備しようとしました。
しかし!いざ自分で一から準備しようとすると、「水は?食料は?」「ラジオは必要?」「ライトは?」など、考えるべきことが多すぎて、結局、挫折しました。
結果的に、必要なものが厳選されてセットになった防災リュックを買う決断をしました!
中身もセットになった防災リュックは、大抵、災害の専門家や防災士が監修しており、被災時に最低限必要なものが厳選されています。
自分で複数の店舗に足を運んで一から選ぶ手間もなく、買い忘れの心配もないことを考えると、多少高価ても、一式揃った防災リュックを選ぶのがおすすめです。
防災リュックの選び方
一口に「防災リュック」と言っても、種類はさまざま。防災リュックを選ぶ際に私が気を付けたポイントを4つご紹介します。
1. 価格の相場と中身の充実度
一人暮らし向けの防災リュックの相場は、1万円〜2万円程度です。
安価なものは、食料や水が入っていない場合や、必要最低限のアイテムしかない場合があります。
一方、高価なものは、ヘルメットや長期保存食、女性向けの衛生用品など、より多くのアイテムが含まれています。
自分が何を重視するかによって、選ぶべき商品は変わってきます。まずは、相場感を把握し、予算と中身のバランスを検討しましょう。
中身の充実度を比べる参考として、政府広報オンラインの情報によると、非常持ち出し品の例は以下の通りです。1
- 飲料水
- 食料品(カップめん、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)
- 貴重品(預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など)
- 救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など)
- ヘルメット、防災ずきん
- マスク
- 軍手
- 懐中電灯
- 衣類
- 下着
- 毛布、タオル
- 携帯ラジオ、予備電池
- 使い捨てカイロ
- ウェットティッシュ
- 洗面用具
2. どこまでセットに頼るか
防災リュックを選ぶ際、どこまでを自分で用意するかを考えると、より効率的な買い物ができるはず!
例えば、食料や水、マスク、ウェットティッシュなど、常備しているものや、使い慣れたものを入れたいという人もいるでしょう。
その場合、食料・水などが含まれていない安価な防災グッズのセットを選び、適宜自分でカスタマイズする方法もあります。
3. 身を守るアイテムの有無
ヘルメットなどの身を守るためのアイテムが含まれているかも、防災リュックを選ぶ上で大きな決め手になります。
4. リュック自体の大きさ
リュックの「大きさ」も重要なポイント!
大きすぎるリュックは、非常時に持ち運びが困難になる可能性があります。重すぎると移動の妨げになり、逆に小さすぎると、後で内容物をカスタマイズするとき、追加で必要なものが入りきらないことも。
実物で重さを確かめるのがいちばんですが、商品説明を見るなどで、中身を含めた重さやリュック自体の容量を確認しておきましょう。
オサメットの防災リュックを紹介!
私が買った防災リュックは、オサメット公式ストア(楽天)の一人用防災リュックです。

決め手は、リュックの中に折りたたみ式の蛇腹収縮式のヘルメット「オサメット」が入っていたことです。
いざというときに頭を守るヘルメットは必須だと感じていたのですが、かさばるのが難点でした。
しかし、このオサメットは薄くたためるので、リュックにすっきりとヘルメットが収まるのが魅力的だと感じ、購入に踏み切りました。
購入当時の内容物は以下の通りです。※2022年6月に購入した商品のため、内容が異なる場合があります。2025年8月30日時点で確認したところ、商品説明のページに記載の内容物は変わっていませんでした。


- 5年保存水500ml x3
- 尾西 携帯おにぎり 鮭味 x1
- 尾西 携帯おにぎり わかめ味 x1
- 尾西 携帯おにぎり 五目おこわ味 x1
- 折りたたみ水タンク10L x1
- ダイナモLEDラジオライト x1
- 緊急簡易トイレ x3回分
- エイドチーム-2(応急処置救急セット) x1
- 軍手 x1
- 蓄光ホイッスル x1
- STONE SUGAR 60g x1
- 3層式マスク(1枚入り)x2
- 非常用保温シート x1
- ポリ袋45リットル(10枚入り)x1
- メッシュケースA5 x1
- レインコート x1
- 防災エアーマット x1
- ウェットタオル大判厚手 x1
- 口内清潔ウェットシート x1
- 超防災ウェットティッシュ x1
- デイバッグ(防災リュック本体) x1
- オサメット x1



防災リュックを買った後は…
セット内容をチェック|定期的に点検を!
防災リュックを購入したら、まずは中身の確認を!
自分が購入した商品に何が入っているのか、取扱説明書を見ながら1つずつ確認しましょう。
懐中電灯やラジオが入っている場合、動作確認も忘れずに行い、電池が必要なものは正しくセットされているかチェックしてください(電池は別売りで、自分で買わなければならない場合もあると思います)。
また、食料品や飲料水の賞味期限も、必ず確認しておきましょう!
そして、いざという時に安心して使える状態にしておくために、防災リュックの中身の点検は最低でも年に一度、定期的に行うことをおすすめします。
防災グッズに限らず、物は使っていなくても時間とともに劣化したり、電池が切れたりします。
賞味期限のある食料品や水はもちろん、使用期限があるグッズも入っている場合、切れていないか確認しましょう。
中身を自由にカスタマイズ
防災リュックの中に余裕があれば、買った後に自分だけのカスタマイズをしましょう。
家族・友人・勤務先の連絡先リストの用意
いざというとき大切な人に連絡が取れるよう、私は防災リュックに防水ポーチを入れ、その中に家族や友人の連絡先、自分の勤務先の電話番号などを書いたメモを入れています。
スマホを見れば連絡先が確認できますが、災害時は通信が不安定になり、バッテリーも切れてしまう可能性があります。
ローリングストックを意識した食料・飲料の入れ替え
多くの防災リュックのセット内容には、食料と水が入っていますが、いざ防災リュックの出番が来たときにすべて賞味期限が切れていた!という事態にならないように気を付けましょう。
私の場合、まだ防災セットに元から入っていた食品や水を消費したことも入れ替えたこともありません。しかし、賞味期限の1月前になったら、普段の生活で消費して、買い置きしているローリングストック用の食料や飲料と入れ替えるつもりです。
ローリングストックとは、食料や水を買い置きし、普段の生活で消費して、また使った分だけ新しく買い足す方法です。
ローリングストックを実践することで、無駄なく、常に新しい備蓄の確保が可能に!詳しくは、こちらの記事で紹介しています。
充電する手段を複数確保
お手持ちのスマホを充電できるツールを用意しておくと安心です。
防災リュックには手回し充電式のラジオやライトが入っていることが多いですが、モバイルバッテリーか乾電池式の充電器なども追加しておきましょう。
私の場合、私が選んだ防災リュックに入っていたラジオ兼ライトが、モバイルバッテリーにもなると説明に書かれてありました。
しかし、実際の災害時は、ラジオかライトとして使うのでいっぱいいっぱいのはず!そう考えた結果、モバイルバッテリーをもう1つ入れることにしました。
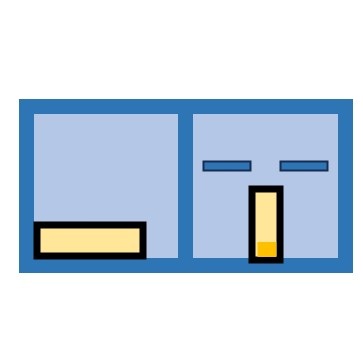
あれもこれも詰め込んだら、防災リュックがかなり重くなった…
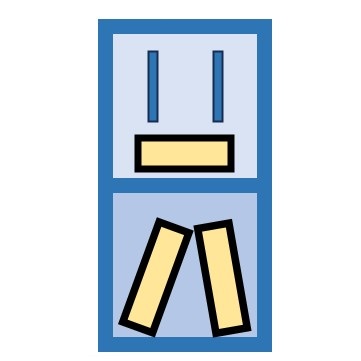
水や食料を入れすぎてないかな?水は1.5〜3L、食料は3日分を目安にしよう。
重いものは背中側に、軽いものは外側にして詰めなおせば多少楽になるかもしれないけど、リュックに空きがあるからと言って詰めすぎは注意!
まとめ:防災リュックを準備して、もしもに備えよう
災害は、いつ起きるかわからないからこそ、日頃から備えることが大切だと思います。
- 何から始めたらいいか迷ったら、「中身が揃った防災リュック」を買うのが効率的。
- 防災リュックに家族の連絡先など、自分に必要なものを追加しよう。
- 防災セットの中身を定期的にチェックする習慣も重要。
自分自身はもちろん、離れて暮らす家族や友人に心配をかけないためにも、ぜひ、自分専用の防災リュックを用意してみてください。
以下の記事では、いつ起こるかわからない地震に備えて、できることをまとめています。この記事と併せて、参考になれば嬉しいです。
- (参照日:2025年11月23日)https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8072.html ↩︎
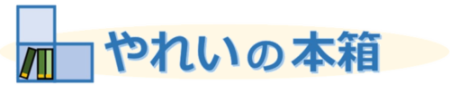

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bc8f23b.d45f20de.4bc8f23c.1ae2cbb3/?me_id=1391217&item_id=10000413&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fosamet%2Fcabinet%2F07853450%2F08022326%2Fkgrs-0030a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)